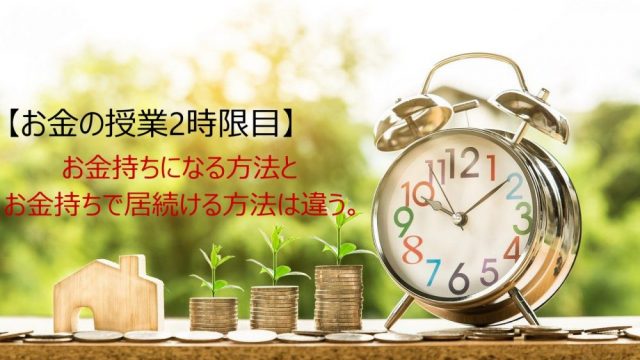彼はいま36歳。
市内の家賃5.6万円のワンルームマンションで過ごしている。
先月、学生時代に知り合った彼女と4年半の交際を経てめでたく結婚。結婚後も引っ越しをする事なく、今まで通りのマンションで生活をしている。
趣味は彼女と共にいくオートキャンプ。それ以外は特にこれといって興味はなし。たまに仲間と飲みに行くことはあるがそれ以外は基本外食もしない。
これだけを聞いてあなたは彼にどんなイメージを持ちましたか?おそらく今あなたの頭の中ではごくごく平凡なサラリーマンを想像したのではないでしょうか?
彼は僕の一番の仲間です。
彼の月収は約50万円。しかしこの50万円は不動産収入。一切仕事をする事なく口座に振り込まれる50万円です。ちょっとあなたの想像とは違ったのではないでしょうか?ではさらにあなたの想像を裏切るとしましょう。
彼はこれ以上不動産を増やすつもりもなく、将来的に何かビジネスを行う予定も一切ない。
まだ36歳という若さを見るとまだまだ上を目指しても良さそうだが…
彼は…お金の正体を知っている
もっと言うのなら『人生の楽しみ方を知っている』ということです。お金は多ければ多いほどイイのは誰だって同じです。だけどお金には絶対的なルールが一つあって、それは…「何かを犠牲にしなければ手に入らない」ということ。これが大前提です。
先ほどお話しした僕の友人は「足りるを知る」…つまり、自分の身の丈を知って必要なお金だけを稼いであとは何も犠牲にせず彼女と楽しい時間を過ごす人生を選択したのです。
彼は沢山のお金や資産を持っているわけではないが1ミリのストレスもありません。
写真をお見せできないのが残念ですが、彼はとってもいい表情をしています。一点の曇りもない「いい表情」とはまさに彼のことを言うのだろうと思う。
昨今、フェイスブックなどSNSの普及で成功者と言われる人達の姿がすぐに見ることが出来ます。
ある成功者は毎晩仲間と楽しそうにお酒を飲んでいる。
ある成功者は都内の高層マンションで優雅な暮らしをしている。
ある成功者は海外へ移住しセミリタイアをしている。
こういった姿を見て「自分もこうなりたい」と考える。しかし、本当にそうなりたいのだろうか?本当にそれがあなたの望む姿なのだろうか?
また最近では色々な教えも蔓延しています。僕も提携して教材を販売したことがあるので
なんとも矛盾している話にはなってしまうが、大富豪の教えやユダヤの教え、華僑の教え、インド人の教えなどなど…これらは間違いなく成功へ辿り着く手段の一つではあります。それは僕も実践してみて間違いのない事だと知っています。
ビジネスは確かに楽しいです。仲間も増える。地位や名誉も得られる。けど、どこか違和感を感じないだろうか?
「ものすごい人と知り合いになれた!」
「今度あそこの会社の役員になる!」
「いよいよ年商100億を目指す!」
「海外でビジネスをスタートさせます!」
「いまこんな投資に興味があるんです!」
文言は違えど結局みんな言っていることは同じ。成功に向かっている自分に酔いしれて気持ちよくなっているだけのように僕には見える。何が言いたいのかというと…
今の世の中…何らかの意図を持って「成功像」を多くの人に植え込み、そうできる人はそうなる人生を歩まされ、そうできない人は劣等感を味わうことになる、お決まりのパターンだということです。つまり人類60億人はたった二つの人種に分類される仕組みを誰かが創り上げたように見えるのです。
ひとつは「成功像」に当てはめられているだけの人。
もうひとつは、それを見て「うらやましい」と思っているだけの人。
けど本来60億人もいれば生き方も60億通りあるはず。なのに知らず知らずのうちに、いま話したどちらかの人種に分類されてしまっているのが現代人だと思うんです。
これを「成功者」というのだろうか?
これを「負け犬」というのだろうか?
僕は違うと思う。言ってしまえば成功者も負け犬も、ただ型にハメられているだけ。シャンパンを飲んだり、高層マンションに住んだり、ビジネスでカッコイイ姿を見せたり、それは「成功像」のほんの一つに過ぎません。
これが悪いと言っているのではなく、あなたは本当にそうなりたいのか?という話です。僕の親友のようにノーストレスで彼女と過ごすのもまた成功。僕のように毎日仲間と大爆笑するのもまた成功。
本当の負け犬とは、なりたい自分を誤魔化して誰かの「成功像」に乗っかかっているだけの奴じゃないだろうか。
これがお金の本質です。便利だけど何かを失う。
昔々、海の向こうの小さな村で人々は物々交換をして暮らしていた。村人みんなが、ニワトリ・卵・ハム・米・パンなどを生産して、それぞれが欲しいものと交換していた。台風や大雨で納屋が壊れた時には、昔からの習慣でお互いに助け合って生きてきた。誰かが助けを必要としていたら、他の者が助けるのは当然だと皆が思っていたのです。
そんなある日…
黒光りした靴に豪華なコートを羽織った見慣れない男が村にやってきて、冷やかな笑みを浮かべながら村の様子を伺っていた。ある農民がハムと交換するために六羽のニワトリを捕まえようと追いかけている姿を見て、その男は笑いを抑えることが出来なかった。
「かわいそうな者たちだ笑!あまりにも原始的すぎる笑!」
その農民の妻がそれを聞きつけこう言った。
「じゃあ、あんたはどうやってあのニワトリを上手に捕まえるか知っているのかい!?」
と憤慨しながら尋ねると、その男はこう言った。
「ニワトリを?それは無理さ!だけど、そんなことより、これらすべての問題を解決する方法を私は知っている」
「ほー?どうやってさ!?」
「じゃあ、教えよう。これから村の者すべてを集めてきてくれ。それと沢山の石ころも持ってきてくれ」
数時間後、村の広場にすべての村人が集まった。男は村人が集めた石ころ全てに念入りに烙印を押した。そして、各家族に10個の石ころを渡し、一つの石ころが一羽のニワトリの価値に相当することを教えた。
「これで、あなたたちは、いちいちニワトリを追いかける必要はないだろう。ニワトリが欲しい時は、誰かに石ころを一つ差し出せばいい。」
皆は「確かにそれはいい!」と豪華なコートを羽織った男に感銘を受けた。
男は帰り際、こう言った。
「ところで、来年の今ごろ、私はまたここを訪れる。その時、皆さんはそれぞれ11個の石ころを私に渡して欲しい。私のおかげで皆さんの暮らしが良くなるのだから、そのお礼だと思って欲しい」
これに対して、ある村民はこう言った。
「どこから11個目の石ころが出てくるんだい?」
この質問に対して、男はこう答えた。
「いずれ分かるよ」
と力強い笑みを浮かべながら…
さて、この話を聞いてちょっと考えてみてください。この村の人口と生産力が一年間、変わらないと仮定してあなたはこの一年、村で何が起こったと思いますか?
ここでのポイントは、男は決して11番目の石ころを、それぞれの家族に渡さなかったということです。
つまり一年後、男に11個の石を渡さなければいけないということは、もしこの村に11の家族しかいなかったら、そのうちの一つの家族はすべての石ころを失うことになります。
いずれにしても、いくつかの家庭は男に11個の石ころを渡せないことになり、その事が次第に恐怖になっていったのです。
台風や大雨で納屋が壊れたとき、他の家族たちは昔と同じように自分たちの時間を使ってでも、その家族を助けようと思っただろうか?それとも、そういった寛大な心は失われていくのだろうか?
実は、この村で起こったのは後者の方でした。烙印を押した石ころは食料の交換としては非常に便利なものだったが、一方でそれまでにあった村人の伝統的な良さをなくしてしまったのです。
この石ころをめぐるゲームは参加者全員の間に競争を生みだしてしまいました。そう…「共走」から「競争」になってしまったのです。
実は、現代の資本主義社会はこの物語の延長線だと言われています。石ころがコインに変わり、コインが紙幣に変わっただけです。
村人は国民へ、黒光りした靴の男は銀行マンへ姿を変えただけなのです。
本質は今と何も変わりありません。そして、ちょっと賢い人なら分かると思いますが「利子」というシステムもこうして生まれたと言われています。
黒光りした靴の男は何もせず、一年間眠っているだけで村人から11枚のコインを受け取ることが出来るのですから。まさに今の銀行そのものです。
そして、もっとも注目すべき点は、紙幣があるばっかりに人間の本来もつ共存という伝統的な良さを無くしてしまったことです。
僕が冒頭言った言葉を覚えていますか?お金には絶対的なルールが一つあって、それは…
『何かを犠牲にしなければ手に入らない』ということ。これが大前提にあると。
現代社会ではその犠牲になるものは『時間』になっているのが一般的ですよね。多くの人は朝8時から夕方17時まで(それ以上という人も)の時間を犠牲にしてお金を得ています。
時間だけならまだいいです。中には時間を掛けて働き過ぎて体を壊してしまう方も多いです。またストレスがたまって体を壊す人だって少なくない。これは健康を犠牲にしてお金を得ているといってもイイでしょう。
これだけではありません。まだあります。家族との時間や子供との時間を犠牲にするということは人間が本来持つ、本能的な幸せや笑顔、心のゆとり、穏やかな空間…そういったものを犠牲にしていると言えるのではないでしょうか。
このように今日まであなたが心から欲しいと願っていたお金は大切な何かを犠牲にして得ていたものなんです。
いや、それらを犠牲にしなければ得られないものと言ってもイイでしょう。ここでいま一度、よーく考えて見てほしい。まだお金が欲しいですか?
言ってきますが、お金が悪いと言っているのではありません。「お金が欲しい」という願望も決して悪くはありません。ただ僕は常々、バランスがすべてだと言ってきました。お金に執着するあまり、本当に欲しいものを見失っては本末転倒です。
冒頭、お話しした僕の親友、彼は「お金は何かを犠牲にしなければ手に入らない」ということをよく知っています。
そして彼は「お金」と「犠牲になるもの」を天秤にかけて「何も犠牲にしたくない」を選んだのです。いまあるお金で何が出来るだろうか?お金が入った時に自分の生活がどう変わるだろうか?
そこを考えたとき、「何も変わらなくていい」を選択するのもあなたなりの「成功」だと思うのです。もう一度ここでハッキリさせておきたいことがある。
お金≠成功
(お金イコール成功ではない)
ということ。考え方ひとつで、あなたはすでに成功を手に入れているのです。だってそうでしょ!世界中のどこか貧しい国の人から見るとあなたの生活はすでに大富豪なみなんですから。ではもう少しお金の正体を見ていきましょう。
これが銀行の本質。いくらでもお金を生み出せる。
「私の一万円札を返してください!!」
窓口の女性行員は一体何のことか分からずポカンとしていると彼はこう続けました。
「あなた達を信用して大事な1万円札を預けたのに“わたしの”1万円札は返ってこない」
これ意味分かりますか?笑
これは実際にあった話なのですが、一人の男性は尊敬する父親の死によって莫大な遺産を受け取りました。
父は生前、一生懸命働いて大きな財産をこの男性に残してくれたそうです。男性は尊敬する父親が残してくれたお金を形見として大事に大事に保管していたのです。
すると、そこへある銀行員がやってきてこう言ったのです。
「その大事なお金を当行へ預けてくれませんか?当行では責任をもってお預かり致しますし、これだけの額であれば利息もそうとう付きますよ」
男性は確かに自宅で保管するのは危険だと思っていたので、この銀行にお金を預けることにしたのです。
“すべての1万円札に父親の名前を記して”
ある日…
この男性は父親のことを思い出して父親が「自分に残してくれた1万円札」を手にしたいと銀行へ行きお金を下ろしました。
ところが、そこで手渡された1万円札には記してあったはずの父親の名前はありませんでした。
「これは“父親の”1万円札ではない」
父親が「自分に残してくれた1万円札」はどこにでも流通している1万円札に変わっていたのです。そこでこの男性は冒頭のようにこう言ったのです。
「あなた達を信用して大事な1万円札を預けたのに“わたしの”1万円札は返ってこない」
銀行側は当然
「それはちょっと…」という返答になったのでした。
あなたはこの話を聞いてどう思いますか?
男性が預けたのは“父親の1万円札”
銀行が預かったのは“1万円”
この感覚の違い。
信用創造という言葉をご存知でしょうか?
銀行は預金という形で多くの人からお金を預かり、預金者がいつでも預金を払い戻せるように、現金を用意しています。しかし、預金者の中には預金をすぐに払い戻す人もいれば、長期間預けておく人もいます。
預金者全員がすぐに預金を払い戻すことはまずないので、銀行は預金の全額を現金で用意しておく必要はありません。そのため銀行は預金の一部を手元に置いておき、残りの預金を企業や個人への貸付けします。そして、貸し付けた企業や個人からは利子を受け取ります。
例えば銀行は100万円を10人の人から預かる。すると預金額は1,000万円になる。この10人が一斉に預金を引き出すことはまずないので半分の500万円を、とりあえず引き出し準備金として置いておき、残りの500万円を企業に年利10%で貸し出します。
すると企業側から毎年50万円を受け取ることが出来ます。銀行は借用書など数枚の紙切れを書くだけで50万円を儲けたことになるのです。
しかも、元手はゼロ円…
リスクは我々、預金者側にある。
これが信用創造です。言い方は悪いですが「銀行」というブランドを乱用してお金を産み出したとも言えます。これが銀行の正体で本質なのです。
だから銀行とは決して【預かり屋】ではないわけです。安心を売り文句にお金を集め、実はそのお金を勝手に他人に貸し出し莫大な利益を生んでいるのです。
「銀行だから預けておいて安全だ!」
と思っているかもしれないけど、彼らはあなたの大事なお金を勝手に他に貸し付けて利益を生んでいるのです。あなたのお金をあなたの知らない人に勝手にね…
冷静に考えると心中穏やかじゃないですよね。それより何よりこんな危険なこと他にないと思いませんか?
人のものを勝手に許可なく使い、いずれ返せばいいだろうという姿勢…それが銀行であり金融の真の姿です。
近代社会ではこれが当たり前かのように行われていますが、古代ギリシアの哲学者アリストテレスは、こう言っています。
「銀行の手口は自然界に反しているのでいずれ崩れる」
しかし、こうも言っているのです。
「利子は驚異的な破壊力を持つ」
銀行の行っていることは他人のお金で金儲けをする…つまり自分は一切リスクを背負わず
金儲けをする卑劣なやり方です。ノーリスク・ハイリターンですからね。
こんな商売他にありますか?せいぜいあるのは「ローリスク・ローリターン」ですよね。ノーリスク・ハイリターンの商売は金融業だけ。逆を言えば、これで潰れるような会社はどれだけ無能なんだ?という話です。
ありましたよね。ノーリスクハイリターンの金融業にも関わらず潰れた会社が…あえて名前は書きませんが。
金融業と聞くとどこか敷居が高いとか、能力が自分より上だとか考えがちですが実は彼らの行っていることは低レベルな誰にでも出来ることなんです。
じゃあ、みんなこの金融業を行えば?と思いませんか??
例えば僕には投資の実績がある。僕が「あなたのお金を増やしますよ!」と声を掛ければ
おそらく相当の金額を集めることが出来るでしょう。これを元手に僕は100%負けない投資を行えばイイわけです。
だけど!!
これは法律違反なんです。国に許可なく勝手にこういったことをやってはダメなんです。なぜでしょうね…不思議ですよね(苦笑)
でも答えは簡単。こんなアホでも稼げるおいしい仕事は独占したい。それが国の本音ですよ。だから意味のない法律を作って、国民が金融業に参加できないようにしているのです。
だけど、そこに目をつけたのが俗にいう「ヤミ金」です。「ヤミ金」と聞くとドラマなどでよく見かける高利貸を想像しますよね。僕はあれもメディアの仕組まれた罠だと思っています。「ヤミ金は怖いよ!絶対に手を出さないでね」と。
だけど僕は、低利のヤミ金を何社も知っています。金利は年利で2.5%、銀行よりちょっと高い程度です。確かにこれは登録のない、違法な金融ですので決して褒められることではないし、それを認めているわけでもありません。
それが大前提ですが、彼らに救われている企業や個人がいるのも確かなんです。銀行ではお金が借りられなくて、どうしようもない場合に彼らに頼る。
こういう闇の部分で助けられている人もいるわけです。独占したいあまり、意味のない法律を作り金融から締め出す国家と、法を犯してまで人の役に立ちたいと思うヤミ金。
さあ。どちらが正義でしょうか?
次回へ続く。